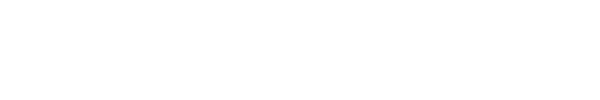人気メモリーのおすすめ製品をご紹介しています。
メモリーは、パソコンや自作PCの快適さを左右する最重要パーツのひとつ。負荷の大きな処理では、メモリクロックが高いほどメモリ帯域幅が増加、実効レイテンシも短縮されれば処理効率の向上が期待できます。
ゲーミング用途であれば、DDR5規格やXMPプロファイルの有無がフレームレートに影響するケースもあります。さらに、省スペースPCや小型フォームファクタ向けにSO-DIMMタイプを選ぶ場面も増えています。各メーカーが展開するヒートスプレッダー付きモデルやRGBライティング搭載モデルも、パフォーマンスとデザイン性の両立を図る上で選定ポイントとなります。
ブラウジングでタブが増えると動作がもたつく、PCゲーム環境を改善したい人はぜひ、見てみてください。
目次より探す
- PC性能を引き出す「メモリー」の重要性
- メモリー選びで知っておくこと
- メモリーの選び方|チェックすべきポイント
- メモリーのおすすめメーカーと代表モデル
- G.SKILL Ripjaws S5シリーズ DDR5 RAM (Intel XMP 3.0) 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30-40-40-96 1.35V デスクトップコンピュータメモリ U-DIMM
- G.SKILL Ripjaws S5 DDR5-6000 32GB メモリキット
- Crucial(クルーシャル)/ 16GBX2枚
- Corsair(コルセア)/ VENGEANCE 32GB(16GBx2) / DDR5-5600MHz
- Kingston(キングストン)FURY デスクトップPC用メモリー DDR5 6000MT/秒 16GB×2枚
- G.Skill AMD EXPO向け DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MT/s
- TEAM DDR5 6000Mhz 16GBx2枚(32GBkit)
- メモリを価格帯で探す
PC性能を引き出す「メモリー」の重要性

パソコンの処理速度や作業をスムーズにして効率を左右するパーツのひとつがメモリー(RAM)です。
CPUやGPUの性能を支える中間領域として、データの一時保管と素早く読み書きできるところです
。
たとえば、ブラウザのタブを多数開く作業や、Adobe Premiere Proでの動画編集、Unreal Engineによるリアルタイムレンダリングなどでは、メモリーの容量と帯域幅が足りないとパフォーマンスに明確な差が出ます。
転送速度や動作電圧の違いがパフォーマンス設計に影響します。また、クロック周波数やCASレイテンシ(CL)といった数値は、処理の応答性を判断する際の重要な指標となります。
メモリー選びで知っておくこと
用途ごとのメモリー構成

使用目的に応じて適切なメモリー構成を選ぶことは、システム全体の安定性と処理効率に関わります。
最新の3Dゲームを快適にプレイする場合、グラフィックスデータやテクスチャの高速なローディング、CPUとGPU間の効率的なデータ転送が求められます。このため、高速なクロック周波数と低いCASレイテンシを備えたメモリーが、高フレームレートの維持やスタッタリングの抑制に貢献します。ゲーミングPCでは16GB以上の容量が推奨され、速度面ではマザーボードとCPUがサポートする上限に近いモデルを選択するとパフォーマンス向上に繋がります。
次に、動画編集、画像処理、3Dモデリング、CAD設計といったクリエイティブワークにおいては、取り扱うデータ量が膨大になる傾向があります。高解像度素材のリアルタイムプレビューや複雑なエフェクト処理、最終的なレンダリングやエンコードの速度は、メモリー容量とバス帯域幅に強く依存します。プロフェッショナルな作業では32~64GB以上の大容量メモリーを、DDR4またはDDR5の広帯域幅を活かせる構成で搭載することが望ましいです。
一方、Webブラウジング、オフィスソフトの利用、メールチェックといった一般的なビジネス・日常用途であれば、複数のアプリケーションを同時に起動するマルチタスク性能が主眼となります。この場合、過剰なスペックは必要なく、8GBまたは16GBの容量があれば多くの作業を快適に行えます。標準的なDDR4メモリーで適切なパフォーマンスを発揮し、コスト効率のよい構成が実現可能です。
サイズはDIMMと小型のSODIMMがあるため、デスクトップPCのメモリをノートパソコンに挿すことができません。購入の際には必ず確認するようにしましょう。
DDR5とDDR4の違い
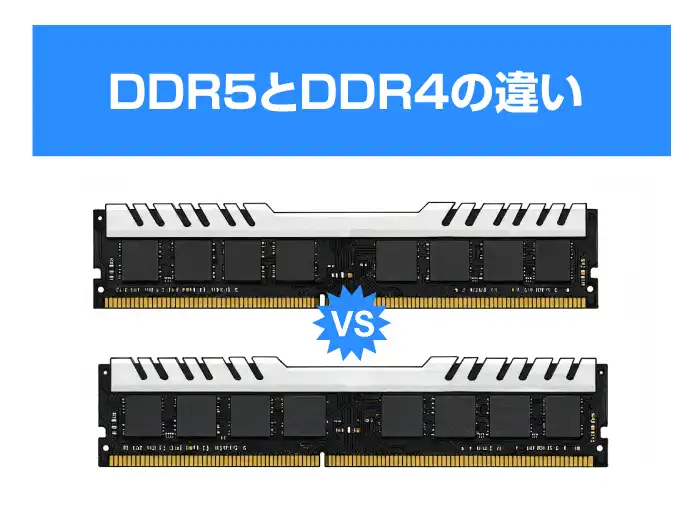
メモリーの選定において、DDR5とDDR4の違いは重要な比較要素です。DDR5は次世代規格として登場し、動作クロックの上限が大幅に引き上げられています。たとえば、DDR4は最大3200MHzが一般的ですが、DDR5は4800MHzからスタートし、6000MHz超のモデルも人気になりつつあります。
帯域幅の拡大により、データ転送効率が高く、マルチコアCPUとの相性も良好です。また、1モジュールあたりのバンク数が増え、命令処理の並列性が強化されています。加えて、電圧が1.1Vへと低下していて、省電力化が図られています。
一方で、DDR5はレイテンシがやや高めで、現状では価格もDDR4より高価です。対応マザーボードやCPUも限定されており、導入には構成の見直しが必要です。コストパフォーマンス重視ならDDR4、高速処理や将来性を見据えるならDDR5という選び方が基本となります。
物理的な形状にも違いがあり、モジュールの切り欠きの位置が違うため、DDR4スロットにDDR5メモリーを、あるいはその逆に差し込むことはできません。マザーボードがどちらの規格に対応しているかを確認する必要があります。
メモリーの選び方|チェックすべきポイント
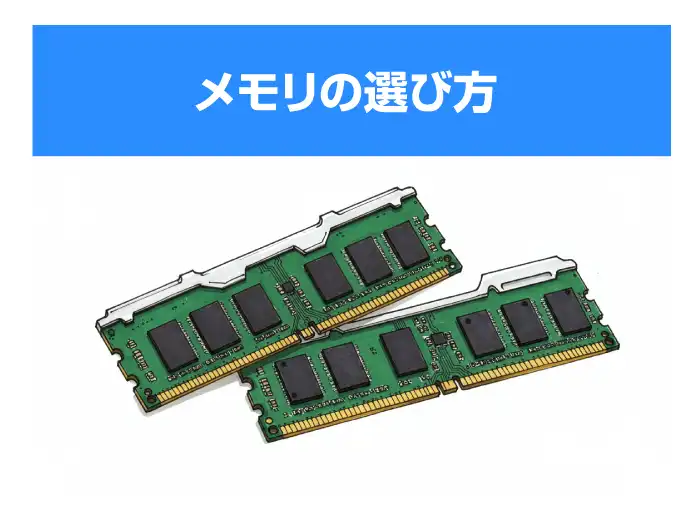
容量(16GB/32GB以上)の目安
メモリー容量の選定は、作業内容と同時実行するアプリケーション数に基づいて判断する必要があります。一般的なブラウジングやOffice系ソフトの使用では16GBが標準的な構成です。
複数タブのブラウザと軽量な画像編集ソフトを併用する場合も、16GBで安定した動作が見込めます。
一方、Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveなどを用いた4K動画編集、Unreal Engineによる3D開発、仮想マシンの並列起動といった高負荷作業では32GB以上を基準とするのが望ましいです。PhotoshopやIllustratorで高解像度データを頻繁に扱う場合も、キャッシュ管理の観点から32GB構成が有利に働きます。
また、DDR5環境では32GB(16GB×2)以上のデュアルチャネル構成が一般化していて、メモリー帯域を最大限に引き出すには必要です。
クロック周波数とレイテンシ(CL)のバランス
メモリー選びにおいて、クロック周波数とレイテンシ(CAS Latency:CL)の関係は見落とせない要素です。クロック周波数はメモリーのデータ転送速度に関わり、数値が高いほど帯域幅が広がります。
一方で、CLはメモリーコントローラーがデータへ読み出すまでの待機サイクル数を表し、低いほど応答速度に優れます。たとえば、DDR4-3200 CL16とDDR4-3600 CL18は、一見すると3600MHzが高速に見えますが、実効レイテンシを比較すると大差はありません。
ゲーミング用途では高クロック重視、ファイル操作やエンコード処理では低レイテンシ重視が基本です。ただし、極端な高クロックや低CLは安定性や価格とのトレードオフがあるため、使用環境に適したバランスのよいモデルを選ぶことが求められます。
デュアルチャネルとシングルチャネルの違い

PCのメモリー性能を最大限に引き出すためには、単に容量や速度だけでなく、メモリーの動作モードも理解することが重要です。主要な動作モードには「シングルチャネル」と「デュアルチャネル」があります。これは、CPU内のメモリーコントローラーとDIMM(メモリーモジュール)間のデータ転送経路の数に関わる概念です。
シングルチャネルモードは、メモリーコントローラーとメモリー間のデータ経路が一つのみで動作する状態です。これは通常、マザーボードのメモリースロットにDIMMを1枚だけ挿した場合や、デュアルチャネルを有効にするためのスロット構成になってない場合に発生します。データが単一の経路を通じて転送されるため、データ転送の「パイプライン」が細くなります。
対照的に、デュアルチャネルモードは、メモリーコントローラーとメモリー間で二つの独立したデータ経路を利用して同時にデータ転送を行う状態です。これは通常、同じ容量と速度を持つ二枚一組(または四枚一組)のDIMMモジュールを、マザーボードが指定するペアのスロットに挿入することで有効になります。デュアルチャネルモードの最大のメリットは、理論上のメモリー帯域幅がシングルチャネル時の約2倍に向上します。
転送速度
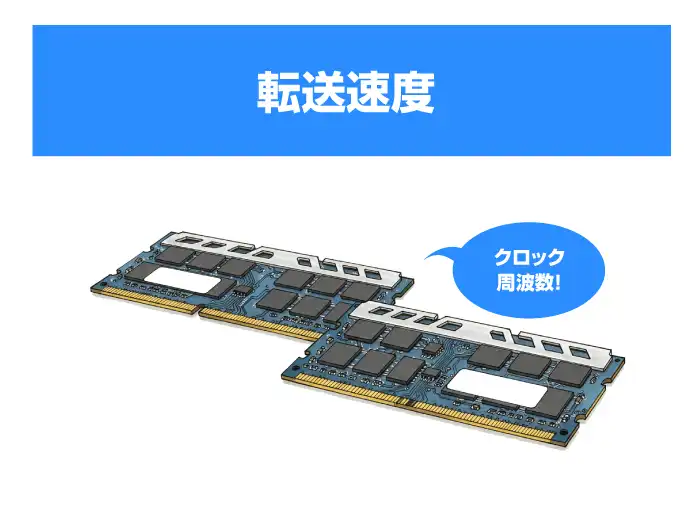
メモリーの性能を左右する指標のひとつが「転送速度」です。これは、1秒間に処理できるデータ量を示し、メモリーモジュールの規格とクロック周波数によって決まります。
たとえば、DDR4-3200は理論上25.6GB/s、DDR5-5600では44.8GB/sの転送速度を持ちます。帯域幅が広いほど、CPUとメモリー間のデータのやり取りがスムーズになり、負荷の高いアプリケーションやマルチタスク環境において処理効率の向上が見込めます。
正確なデータ転送レートを示すのはMT/s表記が目安になります。
RGB搭載モデルの選び方
RGB搭載メモリーは、PC内部の視覚的な魅力を高めるために人気があります。見た目に関しては、RGBの光量や色合い、パターンのカスタマイズ機能が重要なポイントです。多くのモデルは専用ソフトウェアを使って、ライトの色や動き、同期の設定を変更できます。この機能を活用すれば、他のPCパーツとのデザインを統一し、個性的なビジュアルを作り上げることが可能です。
メモリーのおすすめメーカーと代表モデル
G.SKILL Ripjaws S5シリーズ DDR5 RAM (Intel XMP 3.0) 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30-40-40-96 1.35V デスクトップコンピュータメモリ U-DIMM

G.SKILL Ripjaws S5 DDR5-6000 32GB メモリキット
| メモリタイプ | DDR5 U-DIMM 非ECC |
|---|---|
| 容量 | 32GB(16GB×2、デュアルチャネル) |
| 定格速度 | DDR5-6000 6000MT/s CL30-40-40-96 |
| 電圧 | XMP時1.35V、SPD時1.10V |
| OCプロファイル | Intel XMP 3.0 対応 |
| 対応プラットフォーム | Intel Z890/Z790/Z690/B860/B760 |
| ヒートスプレッダー | アルミニウム、マットブラック |
| 高さ | 約33mmのロープロファイル設計 |
特徴
- DDR5-6000 6000MT/sは6000MT/sは“主流の上位帯”として選ばれている速度レンジ。処理のスループット改善が期待できます。
- 32GBデュアルチャネル構成により、同時処理でもメモリ不足を抑えやすい
- CL30-40-40-96と1.35V駆動で、高クロック動作時の応答速度と安定性のバランスを取りやすい
- Intel XMP 3.0プロファイルを使い、BIOS設定を簡略化
- G.SKILL QVLとRAM Configuratorで、マザーボードとの互換性を事前確認でき、自作PCに役立つ
- 同一型番2枚組キット設計で、デスクトップ環境の安定動作しやすい
- 高さ約33mmのロープロファイルで、大型空冷CPUクーラーや小型ケースのクリアランス確保
おすすめしたい人
- プラットフォームがZ790やZ690のDDR5ゲーミングPCで、高クロックメモリを活用したいユーザー
- ブラウジングやOffice作業や動画編集まで同じPCで使うため、32GBクラスのメモリ容量を検討している人
- 物理的な余白が限られた環境で、組み込みたい人
Crucial(クルーシャル)/ 16GBX2枚

Crucial(クルーシャル)PRO デスクトップ用メモリー 16GB×2枚 DDR4-3200は、アルミニウム製のロープロファイルヒートスプレッダーにより、優れた放熱性能とコンパクトなデザインを兼ね備えています。このメモリーは、Intel Core 第8世代から第13世代、AMD Ryzen 1000シリーズから5000シリーズに対応したデスクトップCPUに適合します。さらに、Intel XMP 2.0に対応しているため、パフォーマンスを最適化できます。
DDR4-3200のデータ転送速度は、従来のDDR4-2133メモリーに比べ、1.5倍の速度向上を実現し、システムのパフォーマンスを大幅に向上させます。
また、2,933MT/sまたは2,666MT/sの速度に制限されたシステムでも、ダウンクロック機能により安定した動作が可能です。長期の使用にも耐える無期限保証が付いているのもポイント。
Corsair(コルセア)/ VENGEANCE 32GB(16GBx2) / DDR5-5600MHz

Corsair(コルセア)で、VENGEANCE 32GB(16GBx2) / DDR5-5600MHzです。
デスクトップPC用メモリー VENGEANCE 32GB (16GB×2) CMK32GX5M2B5600Z36 MM8195は、システム性能を最大限に引き出すために設計されたメモリーです。DDR5の革新的な速度により、CPUがデータを迅速に処理でき、処理、レンダリング、バッファリングが従来以上のスピードで行われます。このメモリーは、特に高負荷な作業において、その能力を発揮します。
Corsair iCUEソフトウェアによるオーバークロック機能がサポートされており、より安定した調整が可能です。iCUEを使用すれば、AMD EXPOプロファイルをカスタマイズして保存し、アプリケーションやタスクに最適なパフォーマンスを設定すられます。
さらに、DDR5はDDR4に比べてデータ転送速度が向上していて、高速なデータ処理が要求される作業でもストレスなく対応できます。32GB(16GB×2枚)の容量により、複数のアプリケーションを同時に扱う際にも十分で、快適な作業環境にしたい人にぴったり。
Kingston(キングストン)FURY デスクトップPC用メモリー DDR5 6000MT/秒 16GB×2枚

Kingston FURY Beast DDR5-6000は、高速性と安定性を両立した32GB(16GB×2)構成のデスクトップ向けメモリーです。デュアルチャンネル対応で、メモリー帯域幅を効率よく拡大。1.35V駆動のXMP 3.0プロファイルを搭載し、手動設定を行わずに6000MT/秒までのパフォーマンスを引き出すことが可能です。
内部構造にはオンダイECC(ODECC)を組み込み、クロック上昇時のデータ誤差を低減。さらに、デュアル32ビットサブチャネルとオンモジュールPMIC(電源管理IC)を備え、データ転送と電力制御の効率化を図っています。これにより、動画編集や高解像度ゲーミングといった負荷の高い作業においても安定した動作を保ちます。
CL40のレイテンシ設定は高クロックとのバランスを取り、総合的なパフォーマンスを底上げします。また、薄型ヒートスプレッダーを搭載し、内部エアフローを妨げにくい点も自作PCユーザーにぴったり。
主要マザーボードメーカーからの互換性認証も取得していて、組み込み時のトラブルも発生しにくい製品です。
G.Skill AMD EXPO向け DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MT/s

G.SKILL Trident Z5 Neo RGB(F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR)は、AMD EXPO向けのDDR5メモリーキットで、Ryzen 7000、8000G、9000シリーズに最適化された構成です。DDR5-6000(PC5-48000)に対応し、低レイテンシCL30-38-38-96のタイミング設定により、高負荷環境での動作にも適しています。16GBモジュールを2枚構成としたデュアルチャンネルスペックで、合計32GBのメモリー容量を確保しています。
動作電圧は1.35Vで、EXPOプロファイルを活用すれば、BIOS設定から高クロック環境を再現可能です。RGB LEDによる発光パターンは、マザーボード各社のライティングソフトと同期可能で、見た目にも強いこだわりがある構成向けです。なお、ECC機能は非搭載で、ゲーミングやクリエイティブ用途に特化した設計となっています。
マザーボード側でEXPOプロファイルを有効化することで、公称の6000MT/sに対応。ただし、安定性や対応可否はチップセットやBIOSバージョンに左右されるため、構成選定には注意が必要です。高性能なRyzenプラットフォームを構築するうえで、G.SKILL製メモリーは選択肢の一つに入ります。
TEAM DDR5 6000Mhz 16GBx2枚(32GBkit)

TEAM T-CREATE DDR5-6000(PC5-48000)は、XMP 3.0およびAMD EXPOの両プロファイルに対応した、デスクトップ向けメモリーです。16GB×2枚構成で合計32GBのデュアルチャンネルキットとなっており、標準で6000MHz動作が可能なJEDEC準拠モデルです。10層基板により、高速データ転送時の信号品質を確保しています。
定格速度6000MHzは、対応するマザーボードおよびCPU環境でXMPまたはEXPOを有効にすることで実現します。非対応の構成では、5600MHzや4800MHzなど下位互換の速度で動作します。動作電圧は1.1Vと低く、電力効率も考慮されています。
DDR5環境では、BIOSのバージョンによって最新チップとの互換性に影響が出ることがあります。なお、4枚挿しでの動作安定性は保証対象外となっており、動作周波数の低下や混在構成でのトラブルには注意が必要です。
コストパフォーマンスを重視しつつ、DDR5環境を整えたいユーザーにとって、T-CREATEシリーズは検討に値する選択肢です。
メモリを価格帯で探す
2025年末時点の国内相場感をベースに、ユーザーが価格帯から探しやすい表を作ってみました。
(※2025年はメモリ高騰局面で、特にDDR5が急騰しているため、どの価格帯も「目安レンジ」としてお考えください。
| 価格帯(税込の目安) | 容量・構成の目安 | 主な用途 | 想定される規格・モデル例 |
|---|---|---|---|
| 〜8,000円 |
8〜16GB (8GB×1〜16GB×1) |
・Webブラウジング中心 ・Office、メールなど軽めのビジネス用途 |
・DDR4-2666〜3200の単品モジュール ・DDR5-4800 16GB×1クラスのエントリーモデル |
| 8,000〜20,000円 |
16〜32GB (8GB×2/16GB×2) |
・一般的な在宅ワーク、テレワーク用途 ・ライトなゲーム、写真編集など |
・DDR4-3200 8GB×2 or 16GB×2の主流構成 ・DDR5-4800〜5600の16GB×1〜2枚のコスパ帯 |
| 20,000〜40,000円 |
32〜64GB (16GB×2/32GB×2) |
・フルHD〜WQHDゲーミング ・Premiere Pro などでの動画編集 ・同時に多くのアプリを立ち上げるヘビーユース |
・DDR5-5600〜6000 16GB×2のゲーミング向け ・DDR5 32GB×2エントリー構成(価格高騰で上限寄り) |
| 40,000〜80,000円 |
64〜96GB (32GB×2/48GB×2 など) |
・4K動画編集・3Dレンダリング ・Unreal Engine 等での開発 ・仮想マシンを複数立ち上げる用途 |
・DDR5-6000クラス 32GB×2のハイエンドキット ・RGB搭載やヒートスプレッダ付きのゲーミングモデル |
| 80,000円〜 |
128GB以上 (32GB×4/64GB×2 など) |
・本格的な映像制作スタジオクラスのワークステーション ・大規模3Dシーン、AI学習・推論環境など |
・DDR5-5600〜6000 64GB×2や32GB×4の大容量キット ・EXPO/XMP対応のプロフェッショナル向けモデル |
まとめ
メモリー選びは、PCの性能に大きな影響を与える重要な要素です。用途や作業内容に応じた容量やクロック周波数、レイテンシを見極め、最適なメモリーを選ぶことで、日常的な作業から高負荷なアプリケーションまで快適に処理すられます。
また、デュアルチャネルや転送速度、RGB機能など、パフォーマンスだけでなく、使いやすさや外観要素もあります。最新のメモリーに対応した製品は、性能向上だけでなく、システム全体の快適さを支える重要な役割を果たします。
自分の使用シーンに最適なメモリーを選び、PCのパフォーマンスを最大限に引き出しましょう。
関連パーツ
グラフィックボードおすすめ
▲記事のトップへ「メモリ」